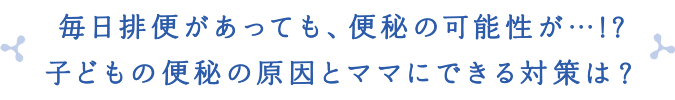子どもの便秘のサイン、見逃さないで!
-
- 日々の様子を思い出しながら、チェックしてみてください!
-
- □トイレの時に、痛がったり、硬い便をする。
- □お水をあまり飲まない。
- □幼稚園や保育園、学校での排便を嫌がる。
- □排便が週に3日未満、もしくは5日以上排便がない。
- □朝トイレに行くことが少ない。
- □小さいコロコロの便や軟らかい便が日に何度も出る。
- ひとつでも当てはまったら便秘のサインかも!

子どもの便秘、発症のピークはなんと2〜3歳。
気付きにくく、悪化が早い、子どもの便秘。
排便を自分でコントロールできるようになる2〜3歳は、便秘の発症のピークと言われています。
排便時の痛みや、不適切なトイレトレーニングなどによる、不快なトイレの経験を繰り返すことで、排便を避けるようになってしまいます。子どもの便秘は「子ども自身が自分で気づかない」「診断が意外と難しい」「悪化が早い」という特徴があるので、小さいうちは、親がしっかりと子どもの排便状況をチェックしてあげましょう。
毎日うんちをしている子どもはたった5割!
子どもの便秘の実態は意外と深刻・・
放置していると、悪循環に陥ることも多い子どもの便秘。
そこで、母親300名とその子どもに調査を実施したところ(※)、便秘傾向にある子どもが約5割と多いことが判明しました。
さらに排便のタイミングでは「帰宅後に済ませることが多い」が最も多く、約半数の子どもが、学校や幼稚園でのトイレを嫌がり、帰宅してから排便をしていることが明らかになりました。
- ※調査概要
-
調査方法:インターネットによるアンケート 調査実施日:2016年3月30日
調査対象:2歳〜小学生までの子どもを持つ母親300人とその子ども

便秘=「うんちが出ない状態」ではない!
毎日うんちが出てても、便秘の可能性が!
毎日排便があっても、出すときに痛みがある場合は便秘の可能性があります。
便秘とは……
- ①便が滞った、または便がでにくい状態
- ②週に3回未満、もしくは5日以上排便がない状態
- ③毎日排便していても、出す時に痛みがあったり、肛門が切れて出血している場合
診療や治療を必要とする状態になった便秘は、「便秘症」と診断され、立派な病気として扱われます。子どもの便秘症は、珍しいことではないのです。その数は10人に1人程度、もしくはそれ以上と考えられています。
お母さんが今すぐ自宅でできる改善方法。
子どもの便秘を治すファーストステップ!
軽症の便秘では、生活・食習慣の見直しでよくなることも。
生活・食習慣に対しての注意は長く続けていくことが大切ですよ。

生活習慣の改善アドバイス
-
①朝のトイレに行く時間をしっかり確保しましょう!
朝食を摂り、トイレに行く時間をしっかり確保するためにも、夜更かし、寝坊を避けるようにしましょう。ただし、排便を無理強いしたり、長時間かけることは避けてください。そして便が出たら、大いに褒めて(喜んで)あげましょう。
-
②便意を感じたら我慢せずにトイレに行く指導をしましょう!
便意を感じているのに、排便を我慢すると便秘が悪化します。学校でトイレを我慢することがないように、家でもしっかり指導しましょう。
-
③日常的に適度な運動をしましょう!
体を動かすことで、腸の運動が活発になり、便通がよくなると言われています。
食生活の改善アドバイス
-
①こまめに水分を補給しましょう!
水分不足は便秘を悪化させます。特に、寝汗をかく子どもは便秘になりやすいので注意してください。運動時などは、脱水が起きないようにこまめに水分を摂るようにしましょう。
-
②便のもとになるものを食べましょう!
便はある程度の量がなければ排出されないため、便のもとになる食物繊維などを多く食べるようにしましょう。スナック菓子やジュースなどは、便のもとになりにくいので避けてください。
-
③ヨーグルトを試してみましょう!
ヨーグルトの整腸効果も多く報告され、また腸内菌叢のバランスを改善するプロバイオティクスの研究も進んでいます。子どもがおやつ感覚で食べられるヨーグルトは、食生活に取り入れやすい食べものです。
大人でもつらい、便秘。
便秘は一旦良くなっても、継続してケアすることが大切です。毎日の生活・食習慣に対しての注意は長く続けていきましょう。