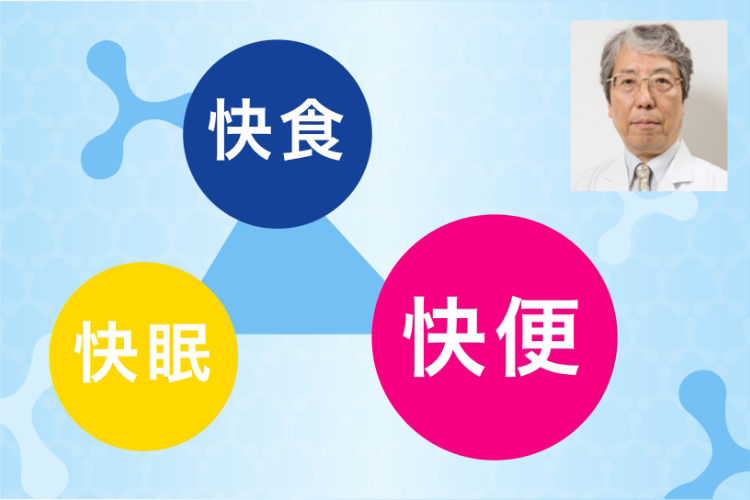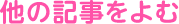大草先生からのメッセージ。
便秘を正しく理解して
「快便」を心がけよう
健康の三大要素は「快食・快眠・快便」と言われますが、その中でも「快便」がとても重要なことをご存知ですか?快便を心がけるためには、そもそも便秘とはどのような状態なのかを正しく理解することが大切です。そこで今回、便秘の定義や健康への影響、便秘対策などについて、順天堂大学大学院 腸内フローラ研究講座 特任教授である大草敏史先生にお話を伺いました。
大草 敏史 先生
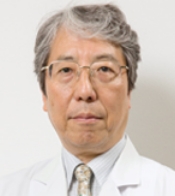
1978年、東京医科歯科大学医学部卒業。1986年に同大学にて医学博士号取得。専門は腸内細菌、消化器内科、消化器内視鏡、慢性便秘症、ピロリ菌感染症。草加市立病院胃腸科医長、東京医科歯科大学医学部第一内科 病棟医長および外来医長、順天堂大学医学部消化器内科学講座 准教授、東京慈恵会医科大学附属柏病院 消化器・肝臓内科診療部長 教授などを経て、2017年4月より順天堂大学大学院腸内フローラ研究講座 特任教授および東京慈恵会医科大学附属柏病院 消化器・肝臓内科 客員教授。慢性便秘の診断・治療研究会代表幹事として「慢性便秘症診療ガイドライン」を出版。
意外と知られていない「便秘」の定義
「便秘」という言葉は日常的に使われますが、実は便秘の定義は難しく、正しく理解されていないケースも少なくありません。
便秘とは、簡単に言うと「本来出すべき便が十分に出ていない状態」のことを言います。最も分かりやすい基準は「便を出す頻度」で、目安として「週に3回以下しか便が出ない場合は便秘である」と言われてきました。最近は、これに加えて「すっきりしたという自覚があるかどうか」という視点も大切にされています。毎日便が出ていても、すっきりしないという残便感がある場合は便秘に含まれるのです。
また、「出す便の量」という観点も大切で、理想は1日1kg〜2kgくらいの便を出すことだと言われています。よく「バナナの形の便は良い便だ」と言われますが、これはあくまでも形状の話。バナナの形の便は、水便でもないし硬い便でもないという点では理想的なのですが、バナナ1本分では1kgの量にはならず、十分だとは言えません。
まとめると、理想的なのは「バナナの形の便が1日1kg以上出ていて、すっきりと残便感がない状態」であると言えます。これに当てはまらない場合は便秘の可能性がありますが、ここで大切なのは本人の自覚です。上記の基準で考えてみると、「自分も実は便秘なのでは……?」と気付く方が多いかもしれません。


便秘になると、想像以上に健康への悪影響がある
便秘になってお腹が張るなどのつらい自覚症状がある場合は、対策を行う方も多いですが、そうでない場合は意外と放置してしまいがちです。しかし、便秘は様々な形で健康への影響があり、長引く前になるべく改善しておくことが大切です。
まず、便秘は肌荒れ・肥満・食欲不振につながりやすいほか、体に毒素がたまることで健康課題も引き起こします。便が長期間にわたって腸内にとどまることで、腸内異常発酵が起きて、腹痛を引き起こすと言われています。肝臓の悪い人が便秘になると、体内でアンモニアを消化しきれなくなり、肝性脳症を引き起こして意識障害が出るケースもあります。
また、最近の研究では、快便を心がけて腸内細菌のバランスを保つことの重要性も分かってきました。腸内細菌の乱れから、パーキンソン病や認知症などの大きな病気にかかりやすくなるとも言われており、身体からのアラートである可能性も考慮に入れるべきです。大きな病気を抱えていない人であっても有害物質が体にとどまることで肌荒れしやすくなることが分かっています。
快便が崩れて便秘になると、イライラしたり気分が優れなくなったりと、精神面にも影響があります。残便感があると気になって何度もトイレに行ったりもするので、仕事や学業に集中できないということもありますし、お腹が張って苦しければ夜もなかなか眠れないこともあるでしょう。このように、便秘になることで、健康面だけでなく生活の質(QOL)もどんどん低下してしまうことになるのです。


便秘薬との付き合い方には注意が必要
便秘に悩む人が取る対策のひとつに便秘薬の服用がありますが、便秘薬との付き合い方には注意が必要です。便秘の症状が重くて体がつらい時には、薬の力を借りることも効果的ですが、習慣的に飲んでよい薬ばかりではありません。
例えば、刺激性の便秘薬は、無理やり腸を動かして便を出させる働きをするため、腸管の粘膜がダメージを受けてしまい腸が動かなくなります。毎日飲み続けることで、だんだん薬が効かなくなり、薬の量を増やしても効果がないといった悪循環に陥ってしまうケースもあります。
最近は、無理やり刺激するのではなく自然に排便できるような便秘薬が増えてきました。小腸に水分を集めて軟便化する薬がその一例で、これらは長期的に服用する際にも安心できます。
生活習慣の改善を心がけ、毎日の“快便習慣”を
健康的な生活を送る上で、「快食・快眠・快便」はとても大切です。食べる方の「快食」には気を遣う人も多いですが、「快便」は意外と見落とされがちです。でも、快便であることの大切さ、つまり便秘の健康への影響を正しく理解しておくことが、健康維持の上で重要になってきます。
そもそも便秘になる原因は、水分不足や繊維不足、運動不足、睡眠不足などの生活習慣であるケースが多いものです。人間には適応能力があるため、多少便秘でも普通に生活ができてしまいますし、それに慣れるとそれに適応した腸になってしまいます。便秘になると腸は本来たまった便を押し出す働きをしなければならないはずなのに、便をためる貯蔵庫のようになってしまいます。短期的にはそれでもどうにかやり過ごすことができても、年をとって体が弱ってきた時に便秘に苦しむことになってしまうため、今から良い排便リズムを身につけていくことが大切です。


「排便習慣」という言葉がありますが、便を出すというのは、ある程度習慣性のあるものです。最初は難しくても、毎日便を出すという習慣をつけるよう心がければ、慣れてくればスムーズにできるようになっていきます。
快便を心がけてしっかりと便を出すというのは、健康面でもとても重要です。しっかりと便を出すことができれば、お腹が空いて、しっかり食べることで体調が安定して、気持ちも満たされます。それが快眠にもつながって、健康的な生活サイクルを保つことができるようになります。そうした健康の基本が「快便」なのです。
手軽に取り入れられる食事習慣として、食物繊維が豊富な食品以外にも、ビフィズス菌やオリゴ糖もおすすめです。善玉菌の代表であるビフィズス菌は腸管を動かしてくれるので、便が出やすくなります。またオリゴ糖はそのビフィズス菌のエサとなり増殖を助けてくれることが期待できます。まずはこうしたものを日常的に取り入れるところから、快便習慣をスタートしてみてはいかがでしょうか。